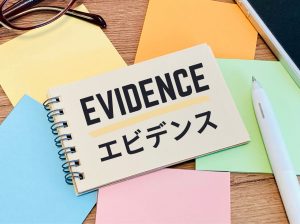「痛みがなかなか取れない…」
「薬を減らして調子が良かったのに、最近また関節が痛くなってきた」
そんなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
今回は、リウマチ治療で薬をほとんど使わずに過ごしていた方が、再び痛みを感じ始めたケースをご紹介しながら、近年わかってきた“痛みの仕組み”と鍼灸のアプローチについてお話しします。

2年間、痛みも腫れもなかったのに…
当院に通われていたリウマチの患者さん。
メトトレキサート(MTX)を2mgまで減薬しており、実質的には薬の効果がなくても問題ない状態でした。
痛みも腫れもなく、2年間は穏やかに過ごされていたのです。
ですが、お孫さんの誕生をきっかけに生活が一変。
娘さんのサポートや育児の手伝いで忙しくなり、通院間隔が徐々に開いていきました。
- 月1回の通院 → 2ヶ月に1回
- さらに3ヶ月に1回に…
すると、関節の痛みや腰痛などの不調が少しずつ現れるようになりました。
鍼治療で改善するはずが、逆に痛みが強く?
腰痛にも対応するため、鍼治療を行いました。
ところが次回来院時、「鍼を受けた後に腰の痛みが強くなった」との声が。
こういったケース、実は時々あるのです。
一見、鍼が悪かったように見えるかもしれませんが、考えられる要因としては…
- お孫さんの世話などで身体的疲労が蓄積
- 鍼治療の間隔が空いていた
- 減薬している今だからこそ、体調管理がより大切
つまり、身体的・精神的なストレスが一気に表に出た状態だったのです。
「痛み=ケガや炎症」だけではないという新しい常識
ここ5年ほどで、痛みに関する研究が大きく進化しました。
これまで「神経や筋肉の損傷が原因」とされていた痛みですが、今ではこんなことがわかっています。
🔍 痛みには「感覚」と「情動」の2つがある
- 感覚的側面:損傷した部位や組織の状態(いわゆる「体の痛み」)
- 情動的側面:怒り・悲しみ・不安・恐怖などの感情が痛みを強める作用
この“情動”が、慢性的な痛みを作り出したり、増幅させたりすることがあるのです。

慢性痛は「心のクセ」にも影響される
特に近年注目されているのが、「破局的思考」という考え方です。
- 「このまま良くならないかも」
- 「また悪化するんじゃないか」
- 「私はもう何をやってもダメなんだ」
こうした思考のクセが、脳に“痛みを強める信号”を送り続けてしまうのです。
リウマチと情動の関係性
今回の患者さんのように、もともと痛みが落ち着いていた方が、生活の変化やストレスによって再び痛みを感じるようになるケースは少なくありません。
お孫さんの世話や娘さんのサポートは、喜びでもありつつ、心身にとっては大きな負担となることもあります。
このような環境変化と情動の影響、そして身体の疲労が重なると、痛みとして現れることがあるのです。
こういうときこそ、鍼灸の出番です
鍼灸は、筋肉や神経に直接アプローチするだけでなく、自律神経のバランスを整え、心と体をつなげる治療法です。
- 筋緊張の緩和
- 血流改善
- 自律神経の安定
- 心の緊張をゆるめる
こうした効果が組み合わさることで、「感覚的な痛み」だけでなく「情動的な痛み」にも働きかけることができるのです。
通院のリズムが大切
今回の患者さんには、「症状が安定するまで、2週間に1回の治療が理想」とお伝えしましたが、理解していただくことは難しいようでした。
「鍼を打ってもらえば、すぐに治る」と思われる方もいらっしゃいますが、痛みの背景には、時間をかけて積み重なったストレスや思考のクセがあることも多いのです。
鍼灸ができること、できないこと
鍼灸は万能ではありません。
ですが、薬では届かない痛みの根本にアプローチできる数少ない方法のひとつです。
- 「薬は飲んでいるけど、痛みが取れない」
- 「ストレスが体に出ている気がする」
- 「体と心の両方をケアしたい」
そんな方にこそ、鍼灸を体験してほしいと心から思っています。
🔚まとめ|リウマチや慢性痛に悩んだら、まずはご相談を
- 痛みには「体」と「心」の両方の原因がある
- 鍼灸はその両方にアプローチできる治療法
- 症状に合わせた適切な通院頻度が効果を高める
- 情動・思考パターンも痛みに大きく関係する
「薬では限界を感じている」
「どこへ行っても原因がわからない」
そんなあなたのために、当院ではじっくり話を聞いて、一人ひとりに合った鍼灸を行っています。
お気軽にご相談ください。